75歳になった時、25歳からの50年間に考えたことを科学・技術、思想、文学、自分史の4つの冊子にまとめて、友人達に配布したあと、次の冊子のテーマを「日常の隙間から」と云うタイトルで、日々考えたことをまとめてみようと思っていた。この構想は漠たるものであり、いわば、人生の余技のように考えていた。もともと短命一族で、男で80歳を超えたものがいない家系なので、75歳を超えて生きることは想定していなかった。しかし、その年はアッと云う間に過ぎていった。
そんな中、死を間じかに迎えた人間は、何を考えるのだろうかに興味を覚えて、手に取ったのが、古書展で見つけた山田風太郎の「人間臨終図鑑」であった。しかしこれは第三者が見た臨終の模様を集めたもので、本人が死を目前にして書いたものではなかった。死を目前にした本人が書いたものでは、渋澤龍彦の最後のエッセイ集「都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト」があり、これは、彼の死1987年8月5日の4か月前の1987年の文学会4月号に掲載されたものだった。しかし、この内容は、もはや病院での出来事を語ったもので死についての論考的要素はなかった。
其の後、西部暹の「保守の遺言」等、死を目前にした思想家の作品も読んだが、死生観に資する内容は三島由紀夫の「豊穣の海」以上のものではなかった。あの小林秀雄にしても、最後の著作「本居宣長」以降の晩年に何を考えたのかは、定かではない。その他にも色々調べたり、読んだりして分かったことは80歳を超えた老人が実際に何を考えて生きているのかについての記述は極めて少ないということであった。そして、それは80歳近くになると気力や思考力が衰え、自らの体験をまとめて、文章にすることが、困難になると云う単純な事実を示していた。
しかし、最近は、人生100年と云われる時代である。100歳まで生きるとすれば、80歳からでも後20年もある。その間、人はどう生きたらよいのだろうか。定年後、様々な集まりに参加するようになったが、知らぬ間に高齢化が進み、気が付けば老人ばかりである。大学時代からの友人達との話題も、病気と健康、グルメと旅行ばかりで、新しい発見がなく面白味がない。日本は、超高齢者社会に突入しつつあるが、残念ながらその高齢社会をどう生きるかの手本は、極めて少ない。手本がない以上自らが作り上げてゆくしかない。この老人達の対局に幼子達がいるが、その存在が逆に道を示してくれるかも知れないと知らされた出来事があった。

数年前の8月の末、4歳になったばかりの孫を庭に連れだし、生えていた風船かずらの実を与えた。その子が実をつかんだとき、その殻が破れ、中から小さな実が出て来た。それにその子がおお!と驚きの感動の声を上げた。
また、ある時、庭にしゃがみこんで、熱心に何かみているので、覗いてみるとそこに小さな蟻が数匹うごめいていた。その小さな生き物をその子は、驚きの目でみていたのである。
さらに、近く公園に行ったとき、突然立ち止まり、シーと唇に指をあてるので何かと耳を澄ますと遠くで微かに小鳥の声がしていた。都会育ちのその子には、小鳥の微かな声が、極めて神秘的な音に思えたらしい。
4歳児にとっては、この世が驚きと感動に満ちた世界であったのである。世界は驚きに満ちている。だからタゴールは「幼子達は、希望と云う火を掲げてこの世に生まれてくる」と詠ったに違いない。我々は、宝の山に住みながら、そのことに気づく感性をなくしているのではないかと反省した出来事であった
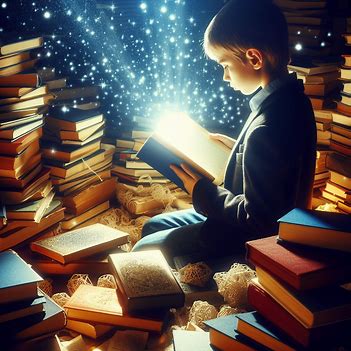
70歳前後の頃ふとしたことをきっかけに丸田町の交差点近くにある古本屋の協同組合の事務所で、開催される古書展に参加するようになった。その古書展は、組合傘下の書店が月に1回共同して古本の即売をする催しで、そこでは、ありとあらゆるジャンルの古書が山積みなって格安で販売されていた。
そこには、一般の書店には展示されていない数十年前に出版され、それ故もう絶版となってしまっているような本も数多く展示されていて、そこで数時間過ごすと思いもかけないような本に出合うことが出来た。しかもその多くは、新品同様のものばかりなのである。
ここで10冊ばかりを2000円以内で購入するのが私の密やかな楽しみとなった。世界にはまだ宝の山が眠っていると思えた。そしてそのことは、今も私に希望の知的波動をおくり続けている。
。75歳までに自分より目上の親族をすべて見送ってようやく自分の世俗の懸案事項を解決出来たと思った。60年前、物理学を学ぶため理学部に入学し、学部で、量子力学と核物理学と統計物理学に取り組んでいた。卒業こそすれ、ここで学んだことを生かすことなく、全く無関係の建築設備の会社に進み、定年まで勤めることになった。未消化に終わった物理学への未練はそのまま、企業人としての人生の底流にずっとうずき続けており、夢の中で、別の人生を見続けていた。その夢のしがらみから解放されたと思ったのは、定年後NPOで、大学関係者と研究活動をともにするようになってからであった。大学での勉強は所詮、哲学や文学と同じく雲の上の学問であったと割り切れるようになったためである。
しかし75歳を過ぎてまもなく、この気持ちを覆すような事件が訪ずれた。量子コンピュータの出現である。60年前自分が取り組んでいた学問が時代の脚光を浴びて歴史の舞台に登場してきたのである。これは、衝撃的な事件であった。僕はあの当時何か重要なことを見落としていたのではないかとの疑念がうまれてきた。それは、60年前の時間に僕を引き戻し、あのフランスの早世の作家アラン・フルリエが、その青春小説「モーヌの大将」で試みたように青春期の出来事の謎解きへと向かわせることになった。そして、それは、僕にとって60年前に戻って自分の別の道の可能性を探ることつまり青春期を再構築することでもある。

法華経の内容が取り入れられたその座禅和讃の冒頭は、「衆生本来仏なり、水と氷のごとくにて水を離れて氷なく、衆生の外に仏なし、衆生近きを知らずして、遠く求むる儚さよ、例えば水の中に居て、喝を叫ぶが如くなり、長者の家の子となりて貧里に迷うに異ならず。」で始まっている。つまり、我々は、宝の山に住みながら、そのことに気づかずにいるとの指摘である。
近くの臨済宗の寺の本堂で、第二、第四の日曜日の早朝行われる座禅会に参加するようになって15年程経つ。この座禅会は、15分の座禅を三回行い、その後で、読経と礼拝を行って終了となる。そのときの経は、般若心経と白隠禅師座禅和讃と四弘誓願文である。つまり曹洞宗であれば、修証義となるところが、臨済宗であるため白隠禅師座禅和讃となっている。
2024年80歳の年に、僕はまた青春を取り戻す旅に出るつもりだ。ゆっくり休むのはこの旅から帰ってからで十分だ。人生はまだ長い。(了)

2024年1月同人誌「ときたま」8号掲載(挿絵は、AIによる)