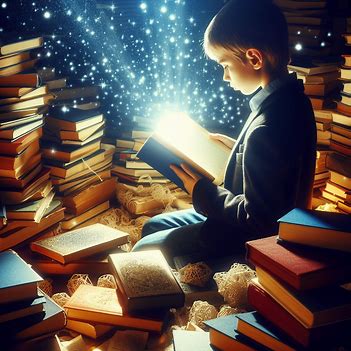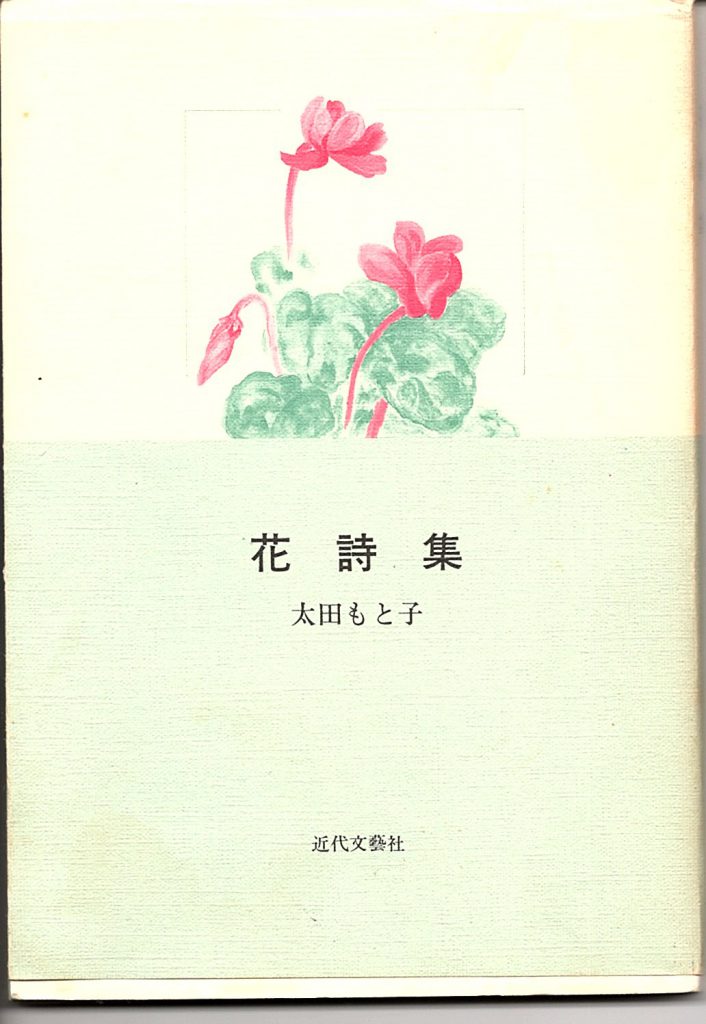はじめに
トランプ政権の関税政策が世界を震撼させている。メディアや数多くの識者がこの現象を取り上げ論評している。そしてその8割がこれを否定的に、2割が少し容認的に取り上げている。しかし、どれも現象論的な論評に留まっているように思われる。そこで自分なりに、感じていることをまとめてみることにする。
トランプの意図とグローバリズムの終焉
トランプがやろうとしていることは、ソ連邦崩壊以後アメリカが作り推し進めて来た世界システムと体制の変革である。これは、一般に(白の)グローバリズムと云う概念で一括できる。それは、自由貿易と市場主義を民主主義のオブラートで包んだ概念である。このグローバリズムは、これは、開かれた自由貿易体制と世界の単一の市場化により世界的な分業システムと効率的な生産システムを構築し、地球規模の経済成長を達成しようとする思想である。これは、社会主義に代わる資本主義の勝利の結果もたらされ、その主役は米国であった。しかし、この文明モデルは、当初からその限界が指摘されていた。それが1975年のローマクラブの成長の限界レポートである。そしてそれへの政策的対応が1992年のブラジルの環境サミットであった。
しかし、ソ連邦崩壊後35年経ってみたとき、このグローバリズムのシステムは、明らかな欠陥と限界を露呈するようになった。その欠陥と限界は、気候変動に対する歯止めの失敗であり、国内外の格差の拡大であり、科学技術と文化のアンバランスないびつな文明社会の誕生である。しかし、この間の経済成長のもたらした恩恵があまりにも大きかったため、世界の大勢は、この路線を肯定するに至っている。
グローバリズムの功罪
問題の根本は、本来狭い地域領域の気候、生態系特性に適合して調和的永続的に営まれるべき生物種としての人間の生存活動が、破壊的な衝撃に直面していることであり、その原因が、各地域の自然、民族、文化、文明の成熟度を無視した急速な単一市場化であり、科学技術や製品の無差別的展開であった。
すなわち、先進国で開発された近代的生産システムは、容易に開発途上国へ移植可能となった。安い労働力の国への近代的生産システムの移植は、先進国の産業構造を金融・管理中心に変え、生産現場の空洞化をもたらす。一方、移植された開発途上国では、移植された生産設備ともたらされた情報による生産物が富の象徴とされ、その地域の自然や風土に適合した技術の確立は放棄されることになった。
先進国では、金融・管理の少数の支配者の富の独占が進み、国内の製造業は衰退し、消費産業が勃興することになる。一方開発途上国では、その地域、地域の文化・自然・風土に根を下ろした科学・技術は、育たず。伝統的社会構造は、崩壊してゆく。このような構造変化は、多かれ少なかれ世界的規模で進行している。
グローバリズムは、世界的視点での生産の効率化を推進する仕組みであるが、それは世界の富を享受できる個人・組織にとっての効率化・最適化であり、ローカルに生活する個人・組織にとっての効率化・最適化ではない。20世紀のグローバル化は、西欧先進国にとっての生産の効率化・最適化であったが、それは裏側から見れば他地域の植民地化によるの自然の収奪であり、労働の奴隷化であり、植民地主義と呼ばれた。現代のグローバリズムは、かつてのプランテーションに替えて分業と云う名のプランテーション的生産の世界的システムの構築であるが、これは、開発途上国の低賃金労働とこの地域の自然環境破壊をもたらしかねない移植産業に支えられている。
資本主義と市場経済
近代ヨーロッパに起源を持つ資本主義・市場主義は、キリスト教的個人主義とピューリタン的倫理観を基礎としており、そこに自由、平等、博愛といった社会的規範意識の成長とともに成熟してきた。市場経済が有益に働くためには、その根底に暗黙の共存意識、すなわち社会常識の存在、ルールの設定、他者の尊重、すなわち法制度の確立、契約の履行と尊重、発明者の権利保護等の様々な規範とそれらを保証する宗教的権威や政治権力の確立等が必要である。
これ等の規範意識と制度の無き、市場経済社会は、弱肉強食社会となりかねない。グローバル経済は、企画・設計と生産現場と消費生活を分離し、そのことによって因果関係を見えにくくするため、フィードバックが働きにくいシステムと云える。
市場経済は、自由な活動と競争原理により、社会を効果的に発展させる仕組みであるが、それを有効に働かせるには、人間の欲望を制御するための様々な工夫が必要であり、それには、文化的成熟とルール確立のための時間が必要である。
ソ連邦崩壊後のこの35年間は、世界的に市場経済が急速に普及した期間であったが、その欠陥を露呈してきた期間でもあった。
すなわち、中国では、文化大革命で、儒教・仏教等の文化的遺産を破壊しつくしたため、その結果の社会主義市場経済は、弱肉強食市場経済と共産党による一党独裁監視社会を出現させてしまった。
ロシアは、文化的未成熟社会のまま、社会主義独裁体制から市場経済に移行したが、少数の特権階級(オリガルヒ)とそれに担がれたプーチンの帝政的専制政治社会を出現させた。
米国では、金融による経済支配と市場の開放により、国内産業の衰退が進む一方で、イノベーションは、活発化し、あらたな情報産業は、勃興したが、貧富の格差は、増大し、製造業は壊滅的打撃をうけ、産業の歪構造化と社会の不安定化をもたらした。
ロシアは、以前として大国であるが、それは地下資源と核兵器と宇宙産業だけの歪な国家であり、国民を豊かにするビジョンなき大国である。
中国は、市場経済導入により急速な近代化をなしたが、それは、国内の低賃金労働者に支えられた製造業による世界市場覇権主義社会であり、ブラックグローバリズムとも云いえるその思想は、周回遅れの新帝国主義社会をもたらし、アメリカ並びに西欧のホワイトグローバリズムとの衝突で行き詰まりをみせている。
この間、世界は、大きく経済成長したが、人口増と地球環境問題に対して有効な対策を実施できなかった。持続可能な開発は、幻想で失敗に終わった。つまり自由貿易と市場主義に訣別する時代がやってきた。
歴史の転換と今後
今までの歴史をみると大きく35~45年周期で変化している。すなわち
第一次世界大戦(1914年から1918年)
第二次世界大戦(1939年から1949年)
ソ連邦の崩壊(1989~1991年)
第二次トランプ政権の誕生(2025年~2029年)
今年は、ソ連邦崩壊から約35年であり、市場経済と自由貿易体制が世界的に拡大してから35年経つ、この間は、米国一強の国連時代であったと云える。
これからの10年間は、このクローバリズが終焉を迎え、新たな秩序形成の時代となるだろう。理想的な世界は貿易と市場を規制し、各国が自国に根を下ろした文化、技術、科学により、独自の自立型産業経済システムを構築することになるが、それには時間がかかるだろう。
次の時代は、グローバリズムへの反動として保護主義的な国家と規制的な国家が主体の世界が出現すると思われるが、それらが形を見せるのにこれから10年程かかるだろう。
そしてそれからさらに30年たった2065年には、再び自由への渇望が芽生え、新な開放的社会が出現するだろう。そしてこの頃になれば、自由な社会にあこがれる人達は、地球外惑星や天体に新世界をもとめて旅立つことになる。この時人類の幼年期は終わるのかも知れない。(了)