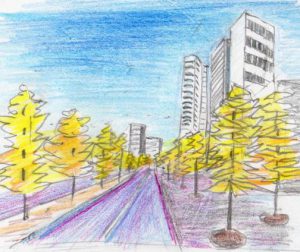 急いで歩いてゆく街路の上に、ふと気が付くと濃紺の空が広がっていて、その深く鮮やかな光景を見つめていると、不意に突きあげてくる郷愁のために、我ながらどうしょうもなく打ち震えてしまう瞬間がある。僕自身の中の何者かが、その光景に触発され、沸騰する瞬間である。
急いで歩いてゆく街路の上に、ふと気が付くと濃紺の空が広がっていて、その深く鮮やかな光景を見つめていると、不意に突きあげてくる郷愁のために、我ながらどうしょうもなく打ち震えてしまう瞬間がある。僕自身の中の何者かが、その光景に触発され、沸騰する瞬間である。
それは、つまらぬ感傷であるかも知れない。しかしたとえそうであったとしても、僕はなおかつ、そうしたものの背後にいる何か未知なるものの存在を確信せざるを得ない。
僕の中にそうしたものがあるということ、そしてそれこそがある意味で僕の思想や行動や生活のエキスのようなものであること、そのことに気づき始めてはや一年になる。
それは始め予感としてあった。徐々に一つの終末が訪れ、何かが生まれようとしていた。
僕は、それを必死で追跡した。感情より先に、そのものの到来より先に僕は言葉でそれを捉えようとした。しかし、それは頑強に言葉を拒絶するかに見えた。それはただ予感としてあった。しかし、それは次第に姿を見せ始めた。僕の生活のほんの稀な瞬間にそれは、僕の内面の膜を激しく揺さぶり未知に向かって予告するように胎動した。そんな時、それは、僕自身の膜の薄い場所を突き破って忽然と顔を出し、僕がまだ、凝視しない内にたちまち、膜の背後に退いてしまった。
しかし、とにかく僕は、それを知り始めた。そのものの感触がまだ指先に残っている、その間に、そのものに僕は大急ぎで言葉を与えた。それはある時には、リルケの「死の核」であると思われ、またある時には、「生の原型」であり、またある時には、シューベルトの「冬の旅」であり、加藤周一の「羊の歌」の世界であると思われた。
しかし、そうした言葉は、そのものではなかった。それらは確かにそのものの一部分、一つの現れではあったのだが・・・。
けれども、そうした日常生活の偶然とも云える一つ一つの出来事や出会いや経験が、一つの終局点に向かって、ある一つの世界に向って追い込んでゆきつつあること、そのことを僕は自覚した。僕はそのものの正体が知りたかった。そのものこそ十年近くも僕が無意識の内に求め続けていたものと確信できたからである。
しかし、そのものは、なかなか正体を見せてはくれなかった。それは確かに以前より頻繁に僕の戸口のすぐ近くまで、訪れるようになっていた。しかしそれは僕が抱きしめようとすると素早く去っていった。僕自身の焦りや恋心をからかう少女の如く、それは僕の手の中からするりと逃げ去ってしまうのだ。しかし、その時の香は、確かに僕が求め続けていたものを暗示していた。
冬が訪れ、春が訪れ、僕とそのものの激しい追跡戦の日々が続いた。ある時は、ビルの谷間に、そしてある時は、群青の下の並木の道に、僕はそのものの映像を求め、見えない地図の上を探索し、進軍した。そして夏、僕の心は、疲労で憔悴し、見つめる僕の眼は、砂漠血に充血し、微かに差し伸べる僕の指先は、強烈な光の中で溺死した。僕自身の中で
一つの「死」が進行していた。思惟は、はやいたずらに感性の中で空転し、見つめる思考場の中に砂漠のような終末が広がっていた。
しかし、長い苦闘の結果、自我の膜は、今や極限まで問い詰められ、一つの薄い不透明な膜としてのみ僕の前にあった。僕は、熱つく海辺で確実に死を迎えた。僕の中の予告が終わり、倒れ伏した僕の上には、幾つもの幻影が降りそそいだ・・・。
そして長い眠りの後に、ふと気づくとそのものは、僕の周辺に漂っていた。それは、透明なままで僕の前にあった。
そのもの、それはかって誤って一人の女性の中に求めたもの、最も親しい友の中に求めたもの、学問の世界に求めたもの、そして結局は、それらの中には、見出し得なかったもの、いやそうした特定の対象の中にあると僕が錯覚したもの。
それは、求めるのではなく共有するところに初めて愛や友情が在り得るもの、始原であり、終末であるもの、僕等の生を貫いて、ずっと先まで広がっているもの。
そのものの到来によって突如として世界が変わるものではなく、そのものの到来によって孤絶するものでもなく、そのものの到来によって初めて僕自身が誕生し、僕の中にリルケの死のようなものが芽生えてくるものである。
それは、エゴイズムや自尊心が無意味になるもの、自己嫌悪の破産するもの、醜さを暖かく支えてくれるもの、対立さえも許しあうもの、悲劇さえも美しくし、悲惨にさえも栄光を与えるもの。
あらゆる理論に対して不敗であり、どんな恋人の愛よりもかるかに深いもの、田村隆一の云う
「詩人だけが発見する失われた海を貫通し、
世界の最も寒冷な空気を引き裂き、
世界の最もデリケートな艦隊を海底に沈め
我々の王と我々の感情の都市を支配するもの」
僕自身の今までの一つ一つの体験や経験が、苦しみや歓びが、悲惨や栄光が、彷徨や安住が、そして限りなく続けられる僕達の生の営みが、ある人との出会いが、その時の会話が、街角の光景が、喫茶店「ラムチー」の片隅で飲むコーヒーの胸に満ちてくるまろやかな情感が、そのものの中でその存在意義を明らかにしてくれるもの。
異なる世紀の異なる国々の一つ一つの事件の中、出会いと別離の中、無数の色彩をなす日々の労働の中、真っ暗な恋の中、悲惨な栄光の中、一つの地方のその風土文化の中、世界史の革命や反革命の中、土着したナショナリズムの中、海を越えるインターナショナリズムの中、それらを貫く全ての思想や意識の中、それら一切を貫いて、すべてを一つの流れの中に導くもの。
人々のその経験や年齢、知識や性別を乗り越えて流れるもの。人間である限り、誰もが空気のように呼吸しているもの、それは確かにそんなものである。それは、感情ではなく、ましてや理論ではなく、しかし理論を拒絶するねのでもなく、そのものの存在によって初めて理論が生命を持ちうるもの、それは確かにそんなものである。
そのもの、それは僕の自我の膜を潜り抜けた彼方に草原のように広がっていた。それは澄み切っていて透明であり、太陽のように明るくはないが、高原の夕暮れのように和やかであった。
それは、特定の言葉を拒絶し、すべての言葉を要求した。それは、固定した領土ではなく、一つの流れであり、無限に広がる大洋のようでもあった。
そのものとの出会いによって、僕は生の地平線をみた。そのものとの出会いによって、僕は都会の窓をみた。歴史のすすり泣きを人間の落ちてゆく地平をみた。幾千万の夜と幾億もの生と死を迎え入れた。そのものとの出会いによって僕は、歴史の落陽を見、欧州史の素顔をみた。愛の生まれてくるカオスを知り、不信が芽生える氷結の木枯らしを知った・
そのものとの出会いによって僕は、自我の彼方を見た。そのものとの出会いによって、僕は僕の母を生み、死は僕の生を生んだ。
それは、詩精神というものが僕の中で覚醒した瞬間であった。
(1970年 陽樹第一号「僕にとってロマンチシズムとはなにか」より)
,
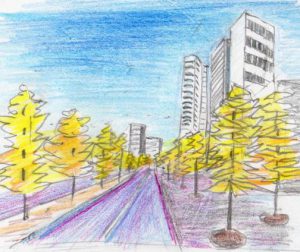 急いで歩いてゆく街路の上に、ふと気が付くと濃紺の空が広がっていて、その深く鮮やかな光景を見つめていると、不意に突きあげてくる郷愁のために、我ながらどうしょうもなく打ち震えてしまう瞬間がある。僕自身の中の何者かが、その光景に触発され、沸騰する瞬間である。
急いで歩いてゆく街路の上に、ふと気が付くと濃紺の空が広がっていて、その深く鮮やかな光景を見つめていると、不意に突きあげてくる郷愁のために、我ながらどうしょうもなく打ち震えてしまう瞬間がある。僕自身の中の何者かが、その光景に触発され、沸騰する瞬間である。