小林秀雄が、モオツアルトを書いていたのは、僕が生まれる前後の出来事であったと最近知って少し驚いた。彼は1902年生まれであるので、終戦当時は、43歳になっていたはずである。しかしそんなに年上であったにもかかわらず、僕は彼がもっと若い人だと思い込んでいた。
その理由は、彼を知ったのがランボーの詩の翻訳家としてであったせいで、その後友人との会話の中で、彼が大阪の道頓堀をうろついていた若き日に「突如としてモオツアルトのト短調シンホニイの有名なテーマが頭の中でなり、そのとき衝撃的な感動を覚え、急いで近くの百貨店でレコードを聴いたが、もはや感動は還ってこなかった」と書いているとの話が、印象に残っているためである。
この話をしてくれた友人は、当時早稲田の仏文科の学生であり、その友人とは、高校時代一夏高蔵寺の禅寺で受験勉強のため生活を共にしたことがあった。東京在住の彼を訪ねたのは、大学生活を半ばすぎた頃であった。何かの理由で上京した僕は、約束もないまま彼が入り浸りであった荻窪駅近くのミニオンとい音楽喫茶を訪ねた。僕としては、彼の日常生活の舞台を覗いてみようという単純な動機であったが、果たして彼がそこに居たのには、驚かされた。その彼が、その頃盛んにモオツァルトの音楽を聴いており、そのことが手紙の中に書かれていた。その彼の影響もあってその頃から僕もモオツァルトの音楽を聴くようになった。
しかし、小林秀雄についてそれほど興味があったわけではなかった。しかし、小林秀雄がト短調シンホニイの有名なテーマが頭の中でなったという異常な体験だけは、深く心に残った。この話を再び記憶の底から呼び戻したのは、全く別の僕自身の体験であった。
1993年営業がらみで企画された「欧州における鉄道の復興と再開発」の視察団の一員として、フランス、スイス、ドイツ、イギリスの4か国を訪れる機会を得、西欧文明の中心地帯を2週間にわたり旅する機会を得た。この旅の途中でスイスのチューリッヒへ立ち寄ったとき、視察団で一緒になった東芝の和田さんという人と親しくなったが、その彼から今チューリッヒの美術館でルーベンス展をやっているので、一緒に見ないかと誘われた。
彼はほとんどが技術屋の視察団の中での文化的な趣味が合った貴重な存在であったこともあり、喜んで行動を共にした。自由な時間は、3時間ばかりであったが、中華料理の簡単な昼食を済ませ、みやげ展でスイスのアーミイナイフを買って、1時間ばかりでルーベンスの絵を見たあと、まだ15分ばかり時間があると云い聖マリアンヌ教会にシャガールのステンドグラスがあるので、それを見ようと誘われ、急いで教会の中に入った。その時素晴らしく美しいステンドグラスをみて言葉で表現しようのない感動を覚えた。その感動を忘れないようにと大急ぎで、それを写したシオリを買って帰ったが、その時の感動を思い出すことはできなかった。この時、あの小林秀雄の話を思い出した。
僕が再び小林秀雄を読んでみようという気になったのは、たまたま古書展でフランス文学者で作家の渋澤龍彦の「悪魔のいる文学史」という本を見つけ、フランスロマン主義とシュールリアリズムの等フランス文学の中でのランボーとその後の思想的潮流の概要を知り、 ようやく、ドイツロマン主義とフランスロマン主義を含めたヨーロッパ文化の底流を統一的に理解するようになったことと関係しており、さらに、ロシアの思想家ニコライ・アレクサンドロヴッイチ・ペルジャエフが「マルクス主義と宗教」という本の中で、マルクス主義は、人間を社会的構成部品とみていて、それ自身が一つの宇宙であるとの視点に欠け、人間における精神的原理の否定、人間の人格と自由を否定すると指摘しているのに触発されたためである。
ペルジャエフは、当初マルクス主義者であったが、後にマルクス主義が、プロレタリアートを新たな選民とする救世主願望(メシア主義)に基づく科学的装いを持つある種の宗教であることを指摘したため、ロシア革命後に国外追放にあっている。社会主義革命の成功と崩壊を思想的にまとめてみようとする過程で、ペルジャエフの指摘に刺激されてあらためて自分を振り返ってみる気になった。
元来理系で唯物論者であった僕は、自然の内に人間を外部から見る見方にならされていて、人間を一つの宇宙としてみる発想にあまり注意を払ってこなかった。何よりも興味の対象が宇宙論等外界にあったためである。しかし、人間を一つの宇宙として考えることに焦点を当てたら何が見えてくるのか。これこそがドイツロマン主義やフランスロマン主義の思想潮流が求め続けたものではないかと思いいたったとき、その観点から小林秀雄を捉えられるのではないかと思い至り、あらためて小林秀雄の書いたものを読んでみることにした。
今回あらためて新潮文庫の「モーツァルト・無常ということ」を読み直してみた。と云うより初めて最後まで読んでみた。彼が、ここで問題にしていたのは、二つの事である。その一つが、音楽や絵画、文学等の作品が我々に与える感動とは何かということであり、今一つは、そうした作品を生み出す天才のエネルギーの源泉・創造性の秘密についてである。この二つの問題について天才的なモーツァルトの作品と凡人モオツアルトの生活の乖離の謎を中心に自分の体験を交えて考えた芸術についての思索の覚書、これが「モーツァルト」の中身であった。
小林秀雄が青春期を迎えた時代は、ヨーロッパの近代の科学主義・合理主義が第一次世界大戦を生み出したことにより大きく揺らぎ、その反動として非合理主義が、ダダイズム・シュールリアリズムとして新たな潮流を形成しつつある時代であった。この時代では、人間とは何かが思想上の大きな問題として問われた時代でもある。つまり人間を外部から科学的に眺めるのではなく、その内部の宇宙に分け入って理解することこれが問題であった。ランボー、ニィーチェ、ドフトエフスキー、ワーグナー、ボードレール、ゲーテ、モーツァルト、ベートーベン、モネ、ゴッボ等、この時代は、こうしたテーマをめぐる素材には、事欠かない。この課題にアクセスするために、小林秀雄は、ほとんど政治的動向には、関心がなかったようであった。戦後「賢い奴は、反省するがよい。僕は馬鹿だから反省しない」と語ったと云われているが、これは、実感であったであろう。戦前・戦後を通して思想が変わらなかった人の一人に柳宗悦がいるが、小林秀雄もそうした人間の一人である。
戦前・戦後で自らを変えなかった男に白州次郎がいるが、その彼の息子のところへ長女明子が嫁いだのも必然性のあることであったかもしれない。ところで小林秀雄は、無神論のように見えるが、彼の奥さんは、光の家の信者であったし、彼の妹の高見沢洵子は、クリスチャンであった。もっともこれは、漫画家長谷川町子が「のらくろ」の作者である夫河水泡(本名高見澤 仲太郎)に弟子入りした関係で、その長谷川町子がクリスチャンであり、一緒に教会に通っていた影響であったらしい。
東大の仏文科にいた頃の中原中也と小林秀雄の関係や長谷川泰子との三角関係の事を詳しく知ったのは、山口県を旅したとき、中原中也の名前を至るところで見かけたことと関係がある。2010年(平成22年)の9月初め山口大学で、空気調和・衛生工学会の大会があり、その大会に参加するため、山口市の湯田温泉に2泊した。この時、大会の合間に市内の瑠璃光寺と少し離れた長門峡でスケッチをしたが、この長門峡の橋のたもとに中原中也の詩碑が立っていた。また、この時、湯田温泉の中に中原中也記念館があったが、この時は、訪れる時間を作れなかった。この2010年には、もう一度その約二か月後10月末に湯田温泉を訪れる機会があった。大学時代の知人達と山口から津和野、萩、そして湯田温泉から厳島神社をめぐる旅に誘われ、この時、中原中也記念館を訪ねることが出来た。
湯田温泉が戦災を免れたこともあって、生家跡に建てられ、2004年にリニューアルそれた近代的な建物には、極めて豊富な資料が展示されていた。この中で、長谷川泰子の「中原中也との愛」(角川文庫2010年1月第5版)を買い求め、旅の途中で読んだ。小林秀雄が、長谷川泰子と同棲したのは、1925年11月から1928年4月(26歳)までの在学中のことである。その直後1929年改造の評論懸賞で「様々な意匠」で第二席を取る。ちなみにこの時の一席は、宮本顕治の「敗北の文学」であったことは、有名な話である。しかし、これ以降評論家としての地位が固まりその5年後の1934年(32歳)に時森喜代美と結婚している。
小林秀雄が、晩年ベルグソンに興味を持ち続けていたことは、有名であるが、それは多分フロイド、ユング、ヤスパース等が指摘した、自我、、超自我、エスと云う人間の無意識領域で鼓動する生命の鼓動とその稲妻のような現出であるラプトウス(夢中、熱狂、自我喪失)と人間の創造活動の関係を哲学的・科学的に明確にしたかったためではなかろうか。
ベルグソンは、無意識の底に蠢く生命の原初的な動きとその方向を「生命のはずみ」としてとらえていたようである。小林秀雄が生きた時代は、アインシュタインの相対性理論や量子力学といった古典的な世界観を破壊する物理理論や宇宙観が誕生しつつあったが、彼は、これらの動きには、全く無関心のように見える。小林秀雄と湯川秀樹との対談を読んでいて感ずるのは、人間を内部から理解しようとする文学と外部から見ようとする科学の統合の難しさである。これを乗り越えるのが、哲学であるかもしれない。
ベルグソンは、生命とは何か、人間とは何かを理解するため絶えず先端科学の動向に目を向け、それを自らの思想や世界観に取り入れようとしていたことを考えると科学的視点無しでベルグソンを理解するには限界があるように思う。小林秀雄が晩年突き当たった壁もこんなところにあったのかもしれない。
小林秀雄も中原中也も裕福な家庭に育ち、食うことに追われる同時代の圧倒的多数とは異なった環境下であったため、第一次世界大戦後の時代の思想的課題を敏感に感じ反応する青春を送ることが出来た。彼らの青春の問題意識は、我々の青春と重なる。しかし、決して裕福とは云えない我々が同じような青春を経験できるまでには、40年もの歳月が必要であった。
今我々は、彼らが捜し求めたものをさらに奥まで極める条件にあるかもしれない。
小林秀雄の「モーツァルト」に導かれ、ラプトウスと精神病と創造性を扱った医師で精神病理学者渡辺哲夫の「創造の星―天才の人類史」2018年講談社選書を読み、人間の合理的意識なるものは、その下に隠されている無意識の世界の超自我やさらにその奥底で蠢く生命体としての無意識の生衝動(エス)云った不合理の大海に浮かぶ小舟のようなものでしかないとあらため整理できた。渡辺哲夫は、彼の手になる関連図書「フロイドとベルグソン」の中でフロイドの云う無意識の世界とベルグソンの云う生命体の生衝動である「生命のはずみ」との関係を扱っていると思われるが、まだその書籍は手元にない。だが、このコロナ下の時間の中で、小林秀雄が僕にとってより身近で理解しやすい存在になったことは事実である。
了
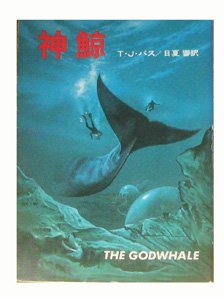 古書展の三冊100円コーナーで見つけた「神鯨」という昭和53年出版のこの本は、まさしく、宝石のように輝くこうした作品の一つである。
古書展の三冊100円コーナーで見つけた「神鯨」という昭和53年出版のこの本は、まさしく、宝石のように輝くこうした作品の一つである。